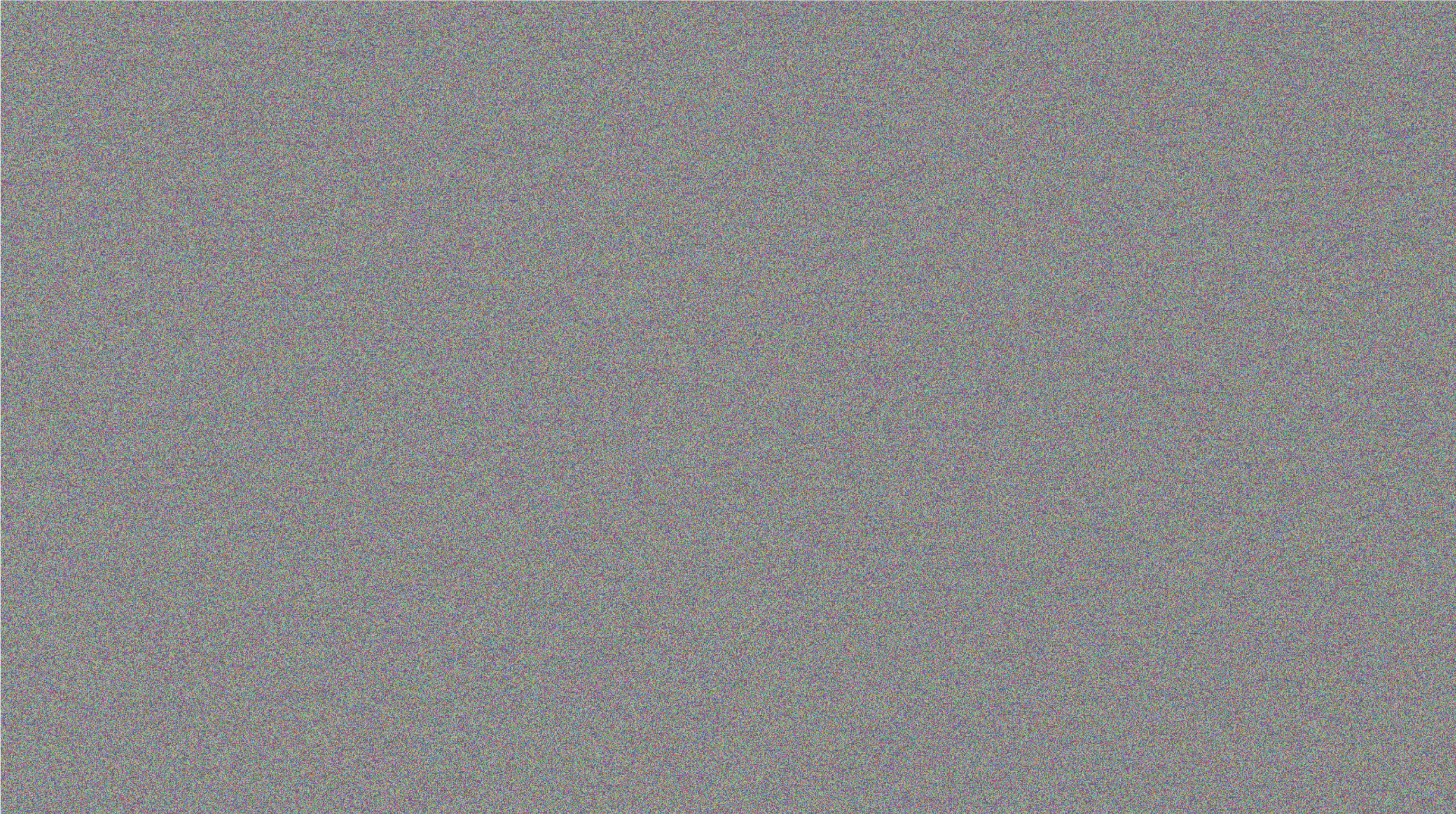10000分の1を磨き上げる研究心。
努力の母数が増えれば、希望の光も増える。
We piece together logic to unravel arrhythmias, then heal them with our own technique. The real thrill lies in that process.
Manabu Nagao 長尾 学
Specialty 循環器基礎研究、脂質異常症
05
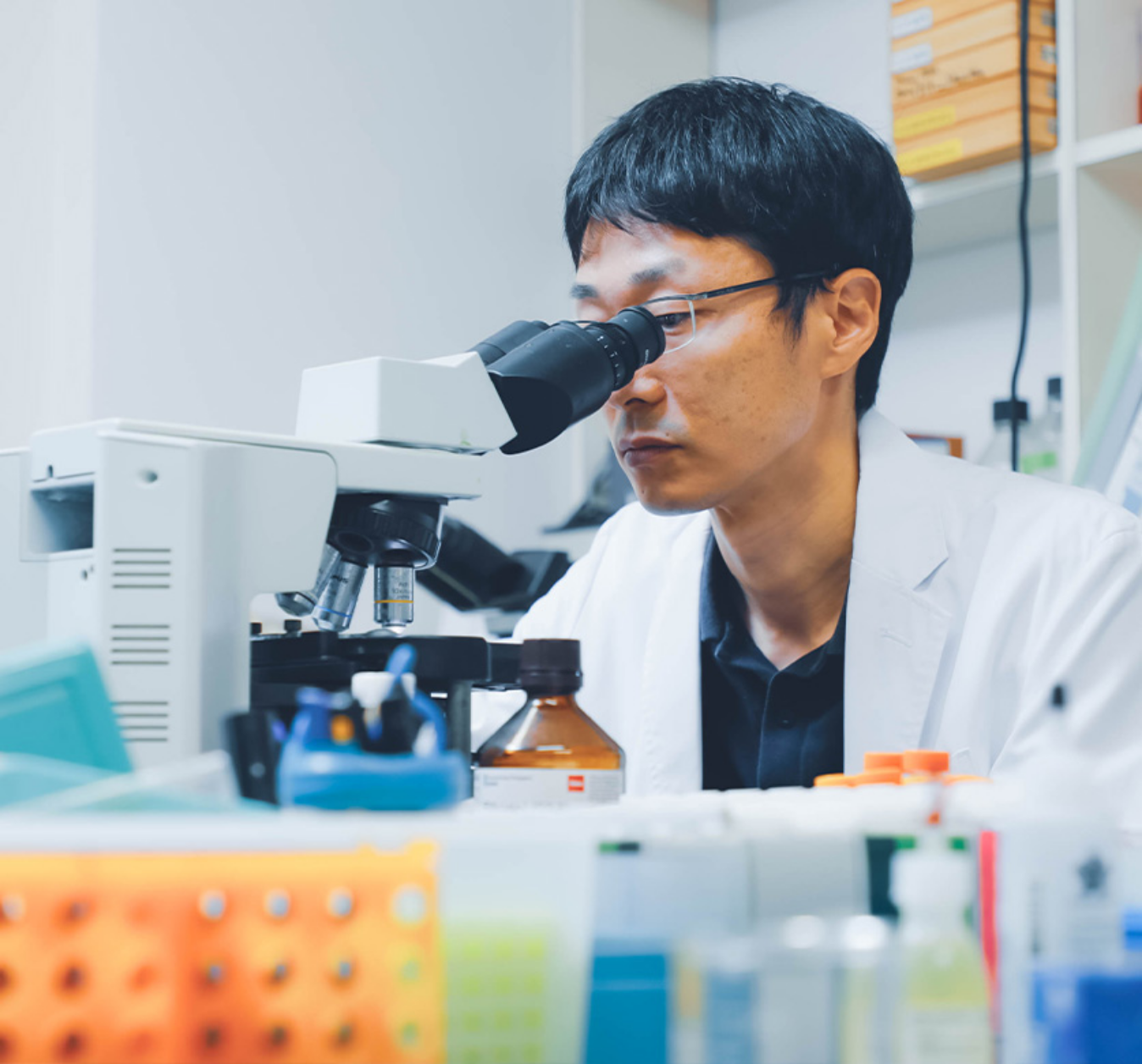
Reasons for choosing the Department of Cardiology, Kobe University
神戸大循環器内科を
選んだ理由
循環器内科医には、病気が治療によって回復するまでの早さに魅力を感じる人が多いと思います。そのスピード感には確かに惹かれますが、それ以上に私が魅力を感じたのは、絶え間なく拍動する心臓という臓器の不思議に迫ること。心臓はシンプルにいうとポンプなので、血液の流速や筋肉の収縮率など、物理的な数値が単位になっていることも多い。
一方で、心臓から出るホルモンが腎臓などの他臓器に作用するというケミカルな部分もあるんですよね。物理と化学、両方の要素を兼ね備えていて、いろんな臓器との関連性が高いことがとても興味深くて。基礎研究は大学でしかできないので、指導医から神戸大への入局を勧められたときは、心臓という魅力的な臓器を深掘りするチャンスだと思いました。
I think many cardiologists are drawn to the speed at which diseases can improve with treatment. That rapid pace is certainly appealing, but what fascinated me even more was delving into the mysteries of the continuously beating heart. Simply put, the heart is a pump, so many aspects—like blood flow velocity or muscle contraction rates—can be measured quantitatively. At the same time, hormones released by the heart affect other organs, like the kidneys, which brings a chemical dimension into play. The heart combines both physical and chemical elements, with complex interactions across multiple organs, which I find incredibly intriguing. Since basic research can only be conducted at a university, when my mentor encouraged me to join Kobe University, I saw it as an opportunity to explore this fascinating organ in depth.
My Heart Moved!” Episodes
「心が動いた!」
エピソード
医局でのキャリアプランは、ある程度の経験を積んだら国内外の他施設に出て専門性を高め、その知見を再び神戸大へ還元するというパターンが一般的です。私の場合は、入局して5年目にスタンフォード大学に留学。世界中から集まった優秀な研究者たちと切磋琢磨することで、自分の視野が大きく広がりました。研究者の雰囲気にも国民性が表れていて、アジアは堅実、イタリアやスペインなどラテン圏は陽気でポジティブ(笑)。そんな文化も価値観も異なる仲間と、「心疾患の病態を解明し、治療に役立てたい」という共通の目標に向かって努力した2年間は、とても刺激的でした。
研究において一番大事なのはアイデアなので、留学中にさまざまな形でアイデアソースをインプットした経験は、今と今後につながる財産になっています。
In our department, the typical career path is to gain some experience, then go to other institutions in Japan or abroad to deepen one’s expertise, and later bring that knowledge back to Kobe University. In my case, I went on a research fellowship at Stanford University in my fifth year after joining the department. Competing and collaborating with brilliant researchers from around the world greatly broadened my perspective. The research environment also reflected cultural differences: for example, Asian researchers tend to be meticulous, while those from Italy or Spain are more cheerful and positive (laughs). Spending two years working with colleagues from diverse backgrounds toward the common goal of understanding heart disease and improving treatment was incredibly stimulating. In research, ideas are the most important resource, and the experience of gathering and processing diverse sources of ideas during my time abroad has become a valuable asset that continues to benefit my work today.

What I value as a doctor
医師として
大切にしていること
目指す場所に辿り着く努力を続けること。現在、外来では主に高コレステロール血症や高中性脂肪など、脂質代謝異常のある患者さんを診ています。研究では、心不全の病態解明を目指して、マウスや細胞を使った基礎研究を行っており、心臓病の患者さんの血液を使ってより簡単に心疾患を診断するためのバイオマーカーの開発も手がけています。研究の中心となる心不全は、例えるなら心臓が風邪をひくようなもので、まだまだわからないことばかり。日本人の100人に1人がなるといわれていて、全身にさまざまな影響を及ぼす上に、一度発症すると完治することが難しい疾患です。
だからこそ予防が大事!予防法の確立や生活習慣の改善などを広く啓蒙していくためにも、病態をしっかり解明したいと思っています。基礎研究はまず仮説を立てて、実験による検証をし、論文化して世の中に発表するのが一連の流れ。
何千、何万の論文があっても、価値のあるものは1本あるかないかという厳しい世界です。地道に研究を続けていくのは難しいけれど、10本の中から選ばれた1本より、10000本から選ばれた1本のほうが磨きがかかった可能性は高いはずですよね。たとえ自分の研究が10000分の1、つまり選ばれる「分子」にはなれなくても、「分母」である10000の中の1本にはなれる。未来の患者さんにとって希望の光となるために、まだ誰も知らない現象を発見する、そんな想いで日々研究に励んでいます。
It’s important to keep striving toward your goals. In my outpatient practice, I mainly see patients with lipid metabolism disorders, such as high cholesterol or elevated triglycerides. In research, I focus on understanding the pathophysiology of heart failure, conducting basic experiments using mice and cultured cells, and developing biomarkers that can help diagnose heart disease more easily from patients’ blood.
Heart failure—the central focus of my research—is somewhat like the heart “catching a cold”: there is still much we do not understand. It is estimated that one in a hundred Japanese people will develop it, and it can affect the entire body. Once it develops, complete recovery is difficult, which is why prevention is so important. I hope to clarify its underlying mechanisms to contribute to preventive strategies and the promotion of healthier lifestyles.
Basic research involves forming a hypothesis, testing it experimentally, and publishing the results. Even with thousands or tens of thousands of papers, only a few are truly valuable. Continuing research patiently is challenging, but a paper selected from 10,000 has likely been honed more carefully than one chosen from just ten. Even if my research doesn’t become the “one in ten thousand” that is recognized, it can still be part of that vast body of work, contributing to the foundation for future discoveries. With the hope of bringing light to patients in the future, I devote myself daily to discovering phenomena that no one has yet observed.
For Future Doctors
未来の
仲間たちへ
一般的に、1つの病院に所属する循環器内科医は数人程度ですが、神戸大には50人以上が在籍しています。これは、臨床・研究・教育のいずれにおいても、多種多様なキャリアパスや価値観に触れる機会が多いということ。入ってみればきっと、人数のメリットを実感すると思いますよ。自分の興味・関心やライフステージに合わせて、モデルとなる先輩医師の姿から多くを学ぶことができる、非常に恵まれた環境がここにはあります。
ぜひ、私たちと一緒に充実した時間を過ごしましょう。
Generally, a single hospital has only a few cardiologists, but at Kobe University, there are more than 50. This means there are many opportunities to encounter diverse career paths and perspectives in clinical practice, research, and education. Once you join, you’ll likely appreciate the advantages of this large team.
Here, you can learn a great deal from senior doctors who can serve as role models, tailored to your own interests, goals, and life stage. It’s an exceptionally supportive environment, and we hope you’ll spend a rewarding and fulfilling time with us.
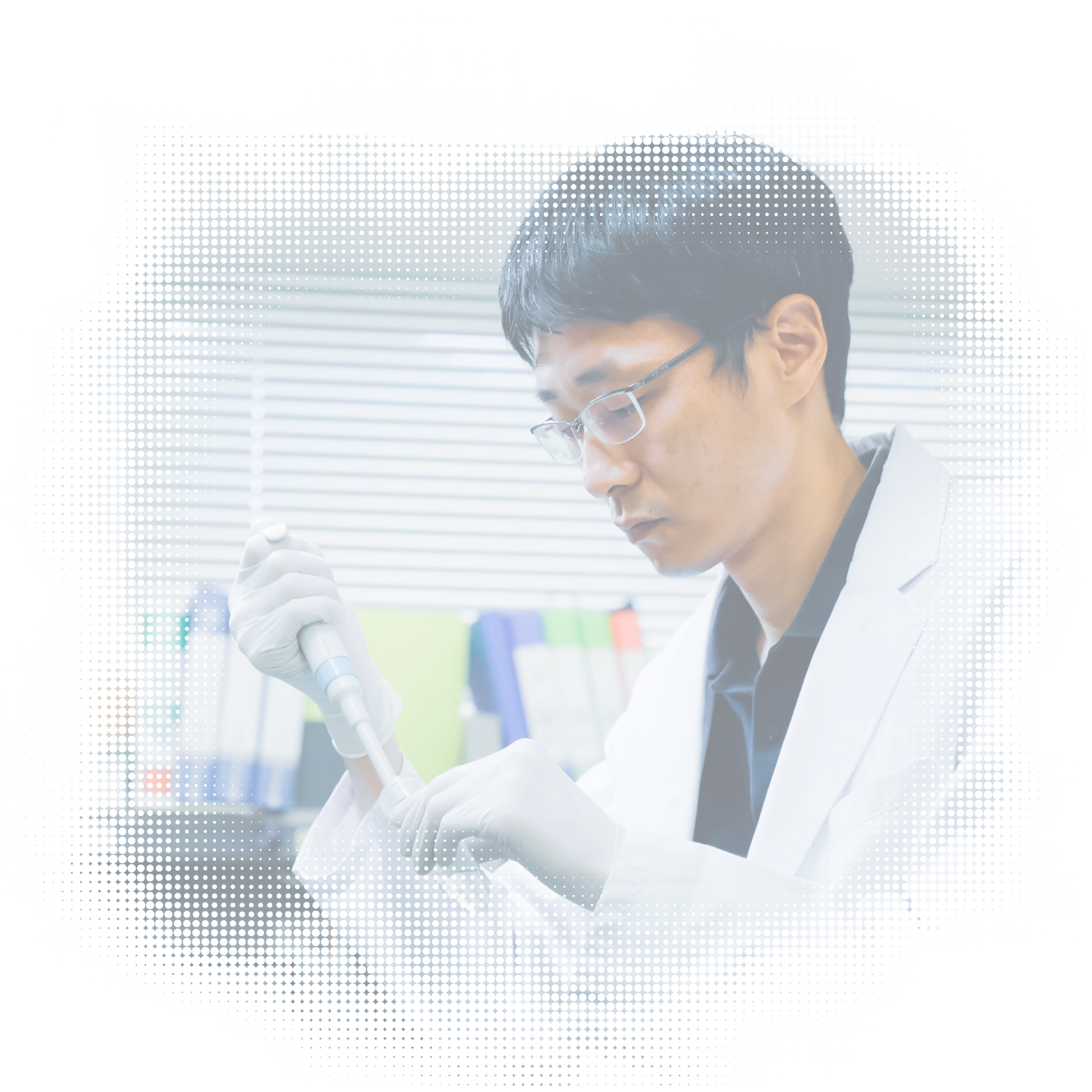
Lively Time わたしがイキイキする瞬間
-
On Work
若い先生と肩を並べて実験しているときや、論文の構成を練っているとき。今後、私がさらに注力したいのは、人材の育成です。これまでの研究や臨床の経験を活かして、若い世代に循環器内科の魅力を伝え、彼らが主体的に挑戦できるようサポートすることがやりがいであり、私自身の挑戦でもあります。 I feel most energized when conducting experiments alongside younger colleagues or when working out the structure of a paper. Moving forward, I want to focus even more on mentoring and developing talent. Leveraging my own experience in research and clinical practice, I hope to convey the appeal of cardiology to the next generation and support them in taking initiative and embracing challenges. This is both a source of fulfillment and a personal challenge for me.
-
Off Time
気の置けない仲間とお酒を飲むとき。生き物と触れ合うのも好きですね。大学では研究のためにマウスを繁殖させていますが、自宅ではメダカの飼育と繁殖を行なっています。計画性のあるタイプなので、メダカが増えすぎないようにきちんとコントロールしています。 I enjoy having drinks with close friends. I also like interacting with living creatures. At the university, I breed mice for research, but at home, I keep and breed medaka fish. Since I’m a rather methodical person, I make sure to carefully control their numbers so they don’t overpopulate.
1 Day Schedule 1日の流れ
-
- 9:00
- 外来診療 / デスクワーク
-
- 13:00
- 研究室で実験 / データの解析 / 学生実習
-
- 15:00
- 研究に関するミーティング
-
- 16:00
- 医局会、その他の会議
インタビュー Other Interview
-
01
Takayoshi Toba 心血管カテーテルインターベンション
鳥羽 敬義
幾多の出会いが、
自分の可能性を広げ
人と人のつながりが、
組織を魅力的にする。Cardiac Catheterization
-
02
Eriko Hisamatsu 重症心不全、心臓移植
久松 恵理子
あったかくなる手足に、
命の重みを感じる。
何度も命を諦めてきた人に
寄り添いたい。Heart Failure & Transplant
-
03
Yu Izawa 循環器画像診断
伊澤 有
人の役に立つ、
それは揺るぎない信念。
「手の施し方」の
よりよい道標を探して。Cardiovascular Imaging
-
04
Mitsuru Takami 不整脈治療
髙見 充
ロジックを組み合わせて
不整脈を紐解き
自らの手技で治す。
そのプロセスにこそ
醍醐味がある。Arrhythmia Treatment